みなさんこんにちは!今回は株式会社の発起設立による登記についてお話します。(小規模での設立を想定しています。)
会社の種類は?
そもそも「会社を作ろう!」と思っても、多くの方は株式会社と合同会社(少ないとは思いますが)しか思い浮かばないのではないでしょうか。
いわゆる会社と呼ばれるものには、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社(及び外国会社)があります。これらに加えて、一般社団法人や一般財団法人等の法人もありますが、今回は割愛します。
これから起業して会社を作る、又は個人事業主としてこれまでやってきたが、法人化しようと検討している方の多くは、株式会社か合同会社を選ぶことになります。今回はその中でも、株式会社の発起設立についてお話します。
発起設立とは
株式会社を設立しようとする際、「発起設立」と「募集設立」の二つの方法があります。
発起設立とは、出資する人又は会社(発起人)が予め決まっており、その人が出資をすることにより設立手続を進めていく方法となります。現在は圧倒的にこの方法で設立するケースが多いです。
募集設立とは、発起人に加えて、出資してくれる人を募集して設立する方法です。当然、出資してくれる人が必ず現れる根拠が無いので、新しく会社を作る場合は募集設立は考えずに発起設立を検討して頂いていいと思います。
何から決めれば・・・
株式会社を設立する際には、主に次の事項を決める必要があります。
- 商号(会社の名前)
- 本店
- 目的
- 株式の譲渡承認機関
- 決算期
- 取締役(その他役員)
- 役員任期
- 資本金(1円でも設立可能ですが、今後の取引等を考えるとおすすめしません。)
- 発行可能株式総数
- 1株の価格(発行株式数)
- 発起人(設立に際して出資し、設立後に株主となる人)
上記以外にも定款に定めることのできる事項はありますが、これらを決定してから司法書士にご相談頂ければ、比較的スムーズに手続が進むと思います。
準備するもの
株式会社の発起設立をする際に準備して頂く書類は、次のものになります。
- 取締役となる方の印鑑証明書(発行後3か月以内。代表取締役以外の方は3か月以内でなくても可ですが、基本的には3か月以内のものをご準備ください。)
- 発起人の印鑑証明書(発行後3か月以内)及び運転免許証表裏コピー又はマイナンバーカード表コピー。これらが無い場合は要相談
- 出資する額を入金した通帳コピー(表紙、表紙次ページ、入金ページの計3ページ。残高があるだけでは駄目で、その場合でも一度出金して、最近の日付で入金して頂く必要があります。)
- 代表取締役となる方の運転免許証等コピー(登記には使用しませんが、ご本人様確認として頂いております。)
書類が揃ったら
必要書類が揃ったら、設立する予定の本店所在地にある都道府県の公証役場にて、定款の認証をしてもらいます。ちゃんとした機関に、定款の内容が間違い無いものであることを証明してもらうようなイメージです。
昔は現地の公証役場に実際に行かなければならなかったのですが、今は郵送とテレビ電話で認証できるようになりました。なので東京に事務所のある私でも、全国どこでも設立依頼を承ることが可能です。
認証が終わり次第、ご希望の日付で設立登記申請をします。
会社の設立登記の場合、登記申請をした日が設立日となりますので、日付をバックデートすることはできません。また、申請する法務局が休みの場合も申請できないので、土日祝日、年末年始も不可となります。
どうしても4月1日がいいとか、1月1日がいいといったお客様もいらっしゃいますが、どんな会社も、休日に設立できた会社はないので、そこはあきらめて頂くほかありません。。。
設立登記の費用
設立登記に係る手続の費用として、まず定款認証に3~5万円前後(資本金による)の費用がかかります。
そして設立登記申請の登録免許税(印紙代)は、資本金×7/1000です。但し、最低15万円はかかります。
つまり、資本金が2000万円程までの場合は、どんなに資本金が少なくても15万円となります。
上記に加えて司法書士への報酬があるので、ご依頼頂いた場合、全部で30万円前後になることが多いです。
設立登記が終わったら
登記が完了するのは、申請してから1週間から10日程度です。
その後、登記内容を証明する、「登記事項証明書」及び「印鑑証明書」の取得が可能となります。
銀行口座の開設や、税務署への届出、従業員を雇う場合は社会保険関係の届出をする必要がありますが、それらには上記の書類が必要となります。
よく「何通取得すればいい?」と聞かれますが、そこは今後取引する銀行等次第かなと。。。
税務関係や社会保険関係の届出についてはコピーで済むようなので、基本的には1通でいいですが、銀行の場合、各金融機関によって取扱いが違うようです。
予約も必要ですし、予め金融機関に質問しておいてもいいかもしれません。
最後に
いかがだったでしょうか?
ここまでお話したのは、最低限の情報です。上記以外にも、業種によっては会社の目的に必ず入れなければいけない文言があったり、会社の機関設計によって必要書類が変わってきたりと、厄介な部分もあります。
専門家である司法書士を頼って頂ければ、適切な対応が可能かと思いますので、どうぞよろしくお願い致します。








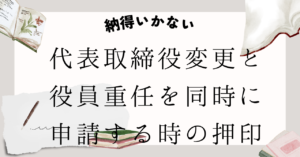
コメント