こんにちは。
ゴールデンウイークも終わってしまいました。
子どもが生まれて初めてのゴールデンウィークは、妻が体調を崩していたため、子どもとご近所散歩三昧でした。
早く遠出できるようになりたいです。。。
今回は、海外の会社が絡む場合の条文等に記載されている「本国」とはどこのことなのか、というお話です。
本国の管轄官庁という文言
発起人が海外の会社で、日本に株式会社を設立するというご依頼がありました。
その発起人の会社が、本店は香港にあるものの、設立準拠法が英国領ヴァージン諸島会社法である会社でした。(ヴァージン諸島絡みの話はまた改めてしようと思います。)
海外の会社が絡んで日本で登記をする場合、ほとんどの場合、「宣誓供述書」という書類を作成し、その書類を「本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲」(商業登記法第129条第2項)の認証を受けたものを準備する必要があります。
これまでほとんど意識してこなかった、この「本国」という言葉。
単純に、「本店が香港だから、香港の公証人の認証か~」と一瞬考える。
が、あれ?当該会社の書類を見るとヴァージン諸島という言葉が至るところに。。。
「これはヴァージン諸島の公証人じゃなくていいのか?そもそも本店が香港なのにヴァージン諸島の法律を根拠にして設立にしていいのか?」と不安に。
そこで色々調べてみました。
「設立準拠法説」と「本店所在地設」
昔は、どのように本国を決定するのか定義がなく、設立準拠法により本国を定める「設立準拠法説」と、本店がある国により判断する「本店所在地説」があり、外国会社と日本の会社はどう区別するんだ、みたいな争いがあったみたいです。
当時も解釈で「設立準拠法説」が取られていたようですが、現在は会社法第2条第1項第2号により「外国の法令に準拠して設立した」法人を外国会社として定めているため、「本国」も設立準拠法を採用した国になるようです。
まとめ
結局、今回のケースだと、本国は英国ということになり、英国の管轄官庁等の認証が必要になります。
ヴァージン諸島はタックスヘイブンであり、現地に法人の人間がいないケースが多く、認証を得るのが大変です。(現地の登録代理人という人が認証を受けてもいいようですが、そこはまた改めてお話します。)
おわり。







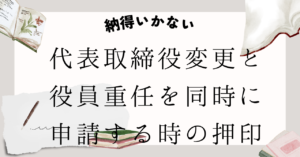
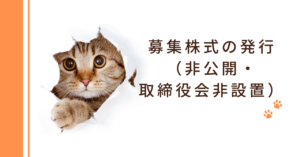
コメント